今回の分科会では、南アルプス(中央構造線エリア)ジオパークの見所5カ所を、グループに分かれて、ガイドシーン(寸劇)を作ってもらいました。
ルールと目標は…
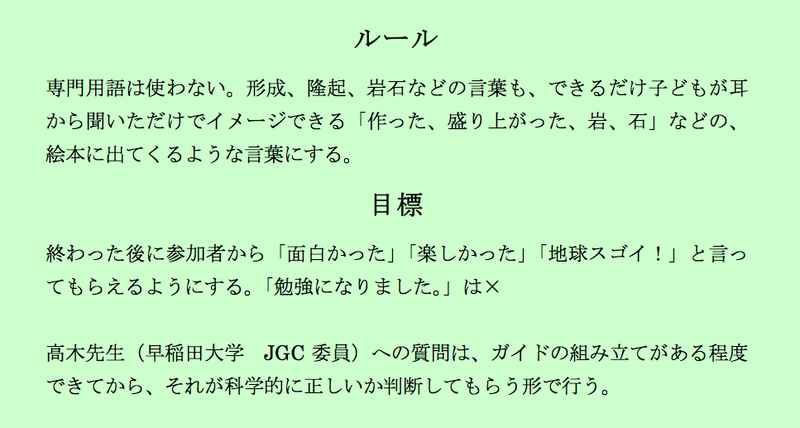
スケジュールは…

お客様の条件は…
東京都内から社内旅行で来て「面白そうだから」とツアーに参加した、地学の専門知識は全くない30~50代の会社の同僚の8名と、どこかのジオパークから来た小学3年生、中学生、ご両親の4名人家族。2組が一緒にツアーに参加していると仮定しました。
まず最初に、私と一緒に分科会をコーディネートした南アルプスジオパークの藤井さんから、南アルプスがどんな場所かの説明がありました。

南アルプスには、富士山に次ぐ国内の高い山がいくつもあるそうです。地球の表面を覆うプレートが押し合って山ができたり、雨が大きな溝を削ったり…ダイナミックな地球の動きを知ることができる南アルプスの魅力を、とてもわかりやすく教えてくれました。(藤井さんの説明に「専門用語を使わずにわかりやすく説明していてスゴイ!」という感想が、聞かれたほどです)
参加人数が73名と多かったので、最初は15チームにわかれ、5分間のガイドシーンを作成してもらいました。各チームに南アルプスのガイドさんが入り、その方の説明と配布資料からガイドシーンを組み立てていきました。

皆さん自己紹介をしながら、楽しそうでした。
後半は3チームが合流。それぞれが作ったものを発表しあい、それをもとに1つのガイドシーンを作ってもらいました。

ここでも、みなさん活発に話しあわれていました。
そして、いよいよ発表。
1名がガイド役で、残りのメンバーはお客様役です。
全ての発表を見ていただきたいのですが、残念ながらそれだと長くなりすぎるので、今日は私が「なるほど~!」と思ったことを、少しだけ報告します。
“入笠山”チーム
入笠山は360度近い角度で八ヶ岳、北・中・南アルプスなどの高い山々が見渡せる場所。ここでガイドをする想定です。

「何でこんなに高い山があると思いますか?」と言う問いかけから、富士山と八ヶ岳の神様が喧嘩したという民話や、南にある伊豆半島にぎゅうぎゅう押された話、噴火との関連を、お客様とやり取りしながら説明していく過程が面白かったです。

入笠山では足もとに“みどり色の石”が見られるそうで「これは恐竜がいたころよりももっと昔に、噴火で海底にできた」と教えてくれました。説明を聞いていたら、この、海の底でできたのに今は山のてっぺんにある“みどり色の石”を見るためだけでも、いつか入笠山に行きたいと本気で思いました。
そしてガイドさんの最後の「日本列島はこんなふうに複雑な、スゴイ変動があってできたんですよね。」という言葉に、チームの方達のメッセージを感じました。
“高遠城址公園”チーム
色の濃いタカトオコヒガンザクラで有名な城址公園で、ガイドする場所は、ヘリから見たこの景色の中を想定しました。

「武田信玄がこの地を納めていた諏訪氏に対し、『おまえら邪魔だ! どけ!』といって、山本勘助に命じて作り直したのが高遠城」と、戦国武将の闘いを子どものケンカみたいに紹介。両側を川にはさまれた高台(河岸段丘)の上にあるので、難攻不落の城だったそうです。歴史の苦手な私でも、スムーズに頭に入り、「スバラシイ!」と思いました。

桜の花が咲く頃は多くの観光客がやってくるとのことで、1日4万人、バスにしたら1000台(!)が、ここを訪れるそう。「桜の花の時期に、ぜひまた来て下さい。」という声かけもされていました。
「糸魚川から来た」というお客様とのやり取りを通じて、日本を東西2つに分ける巨大な溝(フォッサマグナ)についても説明されていました。
“幕岩”チーム
幕岩は、国内でも有数の規模の大きな石灰岩。ここでのガイドを想定しました。

翌日のツアーで私も訪れましたが、白い絶壁が見事でした。
「ジオパークって何か知っている?」「国立公園だから〇〇に注意してね。」などの話題から、ガイドが始まりました。

「山って御岳山のように火山噴火でできるような気がしません? 私もジオを勉強するまでそう思っていたんです。」という話から、目の前の高い山々が火山ではないことを教えてくれました。「年間4mmずつ、ギュギュギュっと盛り上がり、グズグズグズっと崩れている」ということを、ジェスチャーを使って表現してくれたのが、とても分かりやすかったです。
目の前の白い石灰岩の壁が2億年~1億5千年前にできたという歴史を、子ども役の人に「2億って数字、わかるかな?2億円はわかるかな??」と訪ねていたのも面白かったです。(この例えでは、伊豆大島には5万円までしかありませんが・笑)
石灰岩が、運動場の線引きに使う白い粉や、チョークに使われていることも、お客様とのやり取りの中で説明されていました。
"中央構造線・北川露頭”チーム
黒と赤茶色に分かれた崖が、かなり目を引く中央構造線上の崖の1つが北川露頭です。

「崖の右側と左側で色が違いますが右側は海の下で溜まったもの、左側は火山の噴火で出来たもの。触ってみて下さい。崩してはダメですが触るだけなら…柔らかいでしょう?」…と説明は進んでいきます。

中央構造線は、南アルプスでは南北だけど、西に進むと東西に伸びて日本を横断する巨大な溝です。四国西予ジオパークから来たお客様役の人が、「四国西予の近くにも中央構造線がわかる壁がある」と地元を紹介しました。
その後、別のお客様役の人が「私は天草から来ました。中央構造線は九州には全然顔出していないけど、どうなってるんでしょうか?」と質問し、「たぶん九州にもあるんですが、火山灰がいっぱい積もって見えなくなっているのでしょうか?」とガイド役の人が回答。このやり取りが、面白かったです。
中央構造線は日本の広範囲に及ぶので、南アルプスジオパークは各地から来た人に身近感をもって聞いてもらえる語りができる場所なのだなぁ…と思いました。
“遠山川の埋もれ木”チーム
荒涼としたなんとも不思議な風景は、8世紀に地震で山が崩れ川がせき止められて沈んだ森の木が、河川工事と河床の低下で再び現れてできたもの。ここがガイドの舞台です。

このチームのガイドは、ほぼ全てお客様とのやり取りの中で進行。

ガイド「石が転がっている中に柱が立っているような不思議な風景ですが、これはどうやってできたのだと思いますか?」
お客様「全然わかりません!」
ガイド「何かに使っていたのでしょうか?」
お客様「柱かな?」
ガイド「人間が立てた柱ではありません。何がどうなったら、こんなになるんでしょう?」
軽快に続く会話が楽しくて、まるでドラマを見ているようでもありました。
過去の災害とともに、木に恵まれ、米の代わりに木で年貢を納めていたこの地域の、昔の暮らしも教えてくれました。
どの発表も笑いあり、お客様とのやり取りありの楽しいもので、限られた時間(全体で3時間)の中で、これだけのものを作れるガイドさん達に感動しました。
最後に、この地域に最も詳しい専門家の1人、早稲田大学の高木先生からコメントをいただきました。
科学的におかしいと思われる部分へのアドバイスの他、「南アルプスは日本を貫く大きな2本の溝(中央構造線と糸魚川ー静岡線)が交差するスゴイ場所である。石灰岩は二酸化炭素を吸収し調整してくれるエライ存在である。」などの「思い」を語ってくださいました。
本気で「スゴイ」と思っている人の話は、そのままストレートに聞き手に伝わります。
みんなで学びあった後だけに、より一層、高木先生の「スゴイ」の思いが、心に響きました。
終了後、アンケートを取りました。南アルプスの藤井さんが集計してくださることになっており、やがて何らかの形で公開されると思いますので、ここでは簡単に…。
「ジオパークをわかりやすく楽しくガイドするために、どうすれば良いと思いましたか?」の問いに対する皆さんの意見を、私の感覚でザックリと、多い順に並べました。
○一方的に話しをせず、お客様とキャッチボールをしながら、楽しく伝える。
○自分自身も楽しみながら、笑顔で。
○専門用語を使わずに学術的に正しく説明する。
○知識を深めることで、専門用語を使わなくてもすむようになる。
○知識だけでなく、伝えたいメッセージ(感動や驚きなど)が、あることが重要。
○地質だけではなく、草木や民俗的なことも。
○小さな身近なところから、大きな話に持って行く。(高木先生のアドバイスより)
これらの意見が、誰かに一方的に教えられたのではなく、互いに学びあう中から出て来たというところが素敵です。
とにかくいっぱい笑って、皆さんのアイデアや語りに感心した3時間でした。
ガイド分科会に参加された皆さん、お疲れさまでした!
ところで、今回のガイド分科会のコーディネーターは、藤井さんと私でしたが、事前の資料準備では高木先生と中央構造線博物館の河本さんに、進行の組み立てではJGCの中川さん、元・室戸GPで現在は文化庁の柴田さんに、お手伝いいただきました。そして分科会の前日には、中川さん、柴田さんの他に、なぜかたまたま側にいた隠岐ジオパークの平田さんも、夜中0時過ぎまで話し合いに参加してくれました。(なぜ“たまたま居た人”や“担当ではない人”が関わってくれるのかというと“ジオパークは皆で作るもの”だからだと思います!)
ご協力いただいた皆様に、心からお礼申し上げます。
また、今日のブログの風景写真は、幕岩以外は全て、南アルプスジオパークの写真を掲載させていただきました。ありがとうございました!
今回の分科会を土台に、全国のジオパークのガイドの皆さんと一緒に、“ワクワクできるジオ”を伝えていけたら嬉しいです。
(カナ)